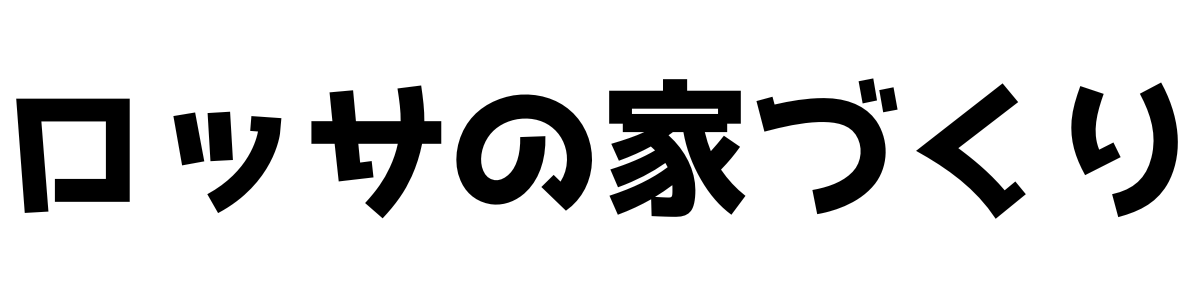悩んでいる人
悩んでいる人土地探しで失敗したらどうしよう……
土地探しはどう行動するのがいいの?
マイホームを建てたいと考えたとき、まず最初にぶつかるのがこの不安ではないでしょうか。
一生に一度の大きな買い物だからこそ、後悔したくないと思う気持ちは当然です。
本記事では、建築士で元ハウスメーカー社員の筆者ぽりんきが、下記3つについてわかりやすく解説していきます。
- 効率的な土地探しの方法
- 失敗しないための方法
- うまくいかない時の対処法
土地探しで必要な知識や注意点がまるっと把握できますよ。
「家族みんなが笑顔で暮らせる理想の土地」を見つけるための大きな手助けになるはずです。
本記事は、下記の方に特におすすめです。
- これから土地探しを始める方
- 何となく探しているけど自信が持てない方
- 家を建てる計画で土地選びを失敗したくない方
後悔しない家づくりのために、まずはこの記事を最後までチェックして、失敗しない土地選びのポイントをしっかり押さえてくださいね!
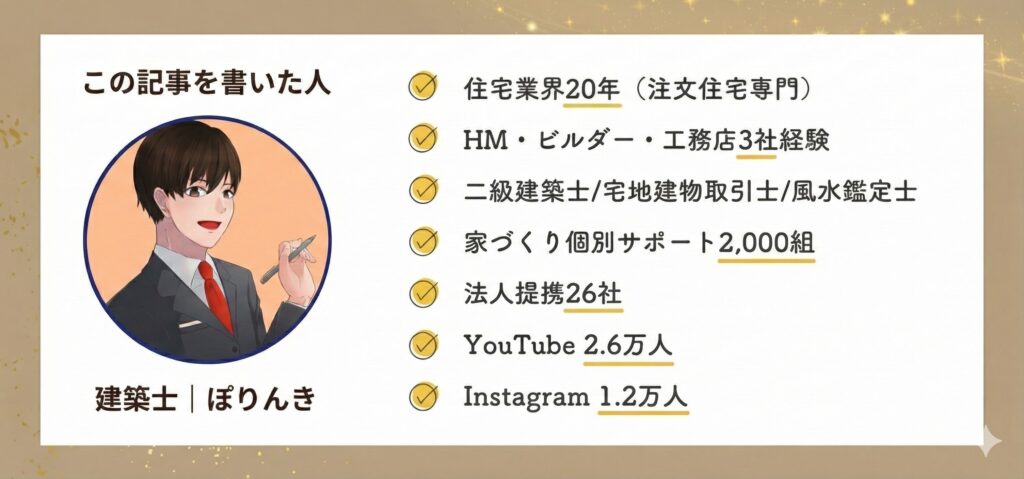
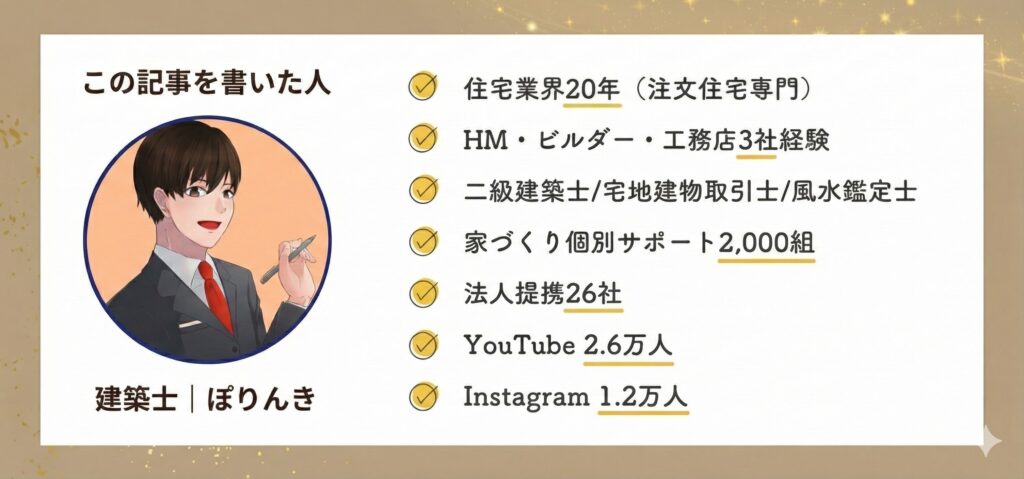
紹介割引実施中!
下記ボタンから希望する住宅会社に
お問い合わせで…
【紹介割引】で理想の住宅が建築可能!



本体価格の3%前後が目安なので90~150万近い割引になることも!!
浮いたお金でオプションを追加したり、最新家電を購入したりと選択肢が広がるので使わないのは完全に損です!!
紹介割引は「当サイト限定」ですので先着枠が埋まる前にお早めに登録くださいね!
紹介可能なハウスメーカー
- ヤマダホームズ
- 桧家住宅
- パパまるハウス
- アキュラホーム
- アイ工務店
- 住友不動産
- ミサワホーム
- トヨタホーム
- ヘーベルハウス
- パナソニックホームズ
- 三井ホーム
- 積水ハウス
【地域ハウスメーカー】
- シアーズホーム/シアーズホームバース(九州全域)
- クレバリーホーム(*神奈川/鳥取/島根/広島のみ)
- 飛鳥住宅(石川県金沢市)
- きゅあホーム(福岡県宗像市)
- 辰巳住研(福岡県古賀市)
- ゼルコバデザイン(大阪府高槻市)
- モリケンハウス(滋賀県大津市)
- アールギャラリー/アールプランナー(愛知/東京/一部:岐阜/三重/神奈川/埼玉)
- アッシュホーム(愛知県稲沢市)
- イトコー(愛知県豊川市)
- WITHDOM (ウィズダム)建築設計(福岡、鹿児島、広島、愛知、長野、静岡、長野、神奈川、岐阜、埼玉、千葉)
- SAWAMURA(澤村)建築設計(滋賀、福井)
- 彩(いろどり)ハウス(いのうえ工務店:埼玉、群馬、栃木)
- オフィスHanako(オフィスはなこ:新潟)
- レスコハウス
※先着順&人数に限りがあります
お早めにお申し込みください。
*割引が存在しない会社もあります
効率的な土地探しの3つの方法


理想の土地を効率よく見つけるには、以下の3つの方法を組み合わせて進めることが大切です。
- 自分でネットや資料請求で情報収集
- ハウスメーカー・住宅会社への相談
- 自分の足で地元の不動産屋巡り
以下、それぞれ解説します。
1_自分でネットや資料請求で情報収集
土地探しを始めたら、まずはネットや資料請求を活用して情報収集を繰り返しましょう。
最初に相場感をつかみ、どんな土地が市場に出ているのかを把握することで、良い土地を見抜く判断力が養われます。



価格交渉を見込んで、予算上限を少し広げて見るのがコツです。
例えば、1,500万円が上限なら2,000万円で検索しましょう。
さらに、週1回以上は必ずチェックし、新着物件が多い木曜・金曜を狙うとチャンスが増えます。
気になる土地があれば、その日に問い合わせや現地確認をするスピード感が重要です。
完璧を求めて長く探し続けるよりも、相場感と選択肢を増やしながら即行動するほうが、理想の土地に早く出会えます。
2_ハウスメーカー・住宅会社への相談
ネットや資料請求である程度目を養ったら、プロの力を借りる段階に進みましょう。
ハウスメーカーや住宅会社には、土地が見つかった際の専門的な調査力があるためです。
ただし紹介を受けた土地は、その住宅会社で建てることが前提です。
土地の仕入れ担当がいるか、地域ネットワークがあるかなどを確認し、最初から信頼できる会社を選ぶことが重要です。
また、住宅会社は業者専用の「レインズ(REINS)」という不動産流通システムを使って土地情報を検索できますが、情報自体は一般サイトと大差はありません。
土地情報の入手よりも、見つかった土地の”プロによる迅速な調査・判断”を期待して依頼しましょう。
\ 無料・たった1分・建築士が監修 /
3_自分の足で地元の不動産屋巡り
本気で良い土地を探すなら、自分の足で地元の不動産屋を巡ることが一番効果的です。
なぜなら不動産業界には売主・買主を同時に担当して仲介手数料を両方から得たいという構造があり、良い物件を他社に回さず自社で囲い込むことが多いためです。



最低でも複数社は地元の不動産屋を回り、直接話を聞くことをおすすめします。
不動産屋巡りのコツは、下記のとおりです。
- 街中にある不動産屋に飛び込みで入る
- 分譲地の旗看板から看板元を調べて訪問する
- Googleマップで「エリア名+不動産」で検索してリストアップする
- 気になる物件の取り扱い業者に直接行って詳しく聞く
直接訪問して顔を覚えてもらうことで、まだネットに出ていない情報を優先的に紹介してもらえる可能性も高まります。
土地探しで失敗しない方法 10選
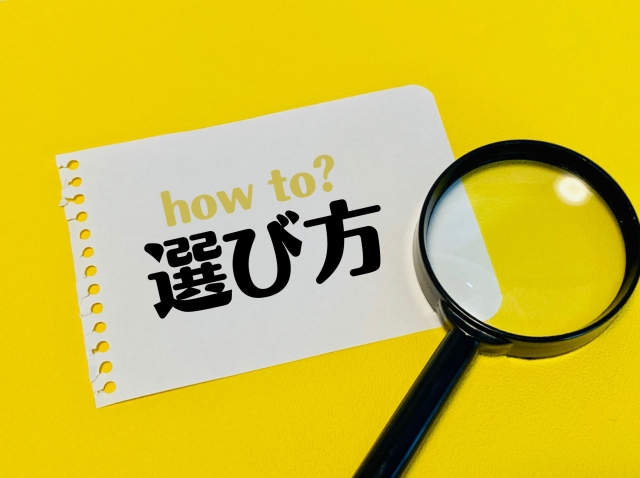
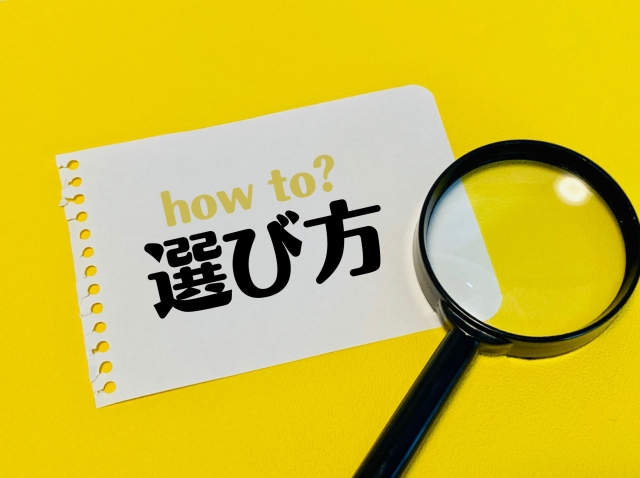
土地探しで失敗を避けるには、下記の10の方法を実践することが重要です。
- 総額予算の決定と適切な配分
- 住宅会社選定と土地探しの連携
- 用途地域・建ぺい率など法規制の確認
- 地盤調査と追加工事のリスク確認
- 道路・インフラの状況を確認
- ハザードマップで災害リスクを把握
- 様々な条件での現地確認とリサーチ
- 境界杭・測量状況の確認
- 安い土地の隠れたコストを確認
- 条件7〜8割での早期決断
10の方法を事前に実践することで、安心して理想の土地を見つけられる可能性が高まります。
1_総額予算の決定と適切な配分
土地探しで最も大切なのは、土地・建物を合わせた総額予算を最初に決めることです。
土地代だけで考えると、後から造成や地盤改良、外構工事などの費用が重なり、結局予算オーバーになるリスクが高まります。
総額予算の配分の目安は、下記のとおりです。
- 土地代:30~40%
- 建物本体:40~50%
- 付帯工事・諸費用など:20%程度
水道引き込みや擁壁工事、地盤改良で数十万〜300万円程度かかることも珍しくありません。
土地を決める前に建物を含めた資金計画を立て、「土地にはここまで」と上限を決めるのが失敗しない最大のコツです。
2_住宅会社選定と土地探しの連携
土地探しで失敗しないためには、先に住宅会社を決めてから土地を探す方法がおすすめです。
建築基準法や造成、インフラ工事などの専門知識を持つ住宅会社がいれば、土地の選定から調査までスムーズに進みます。
先に建築会社を決めるメリットは次のとおりです。
- 理想の家づくりを前提に土地を選べる
- 現地調査や役所調査、業者見積もりを迅速に依頼できる
- 造成費用など土地にかかる実質コストを正確に把握できる
不動産会社は法律や取引に強いものの、設計や工事に関しては住宅会社の方がより深い知見を持っています。
良い土地は競争が激しく、決断の早さがカギを握ります。
住宅会社を先に決めておくことで、土地探しのリスクを減らし、安心して候補を絞ることができます。
実際に多くの方が、信頼できる住宅会社のサポートを受けながら、理想の土地と出会っています。
でも、「どの会社に相談すればいいの?」と迷ってしまうこともありますよね。



私は建築士として18年以上、2,000組以上の家づくりをサポートしてきました。全国の住宅会社をご紹介できます!
気になる方は、ぜひ下記のボタンからご登録ください。
理想の家づくりの第一歩を一緒に踏み出しましょう。
\ 無料・たった1分・建築士が監修 /


3_用途地域・建ぺい率など法規制の確認
土地には「どんな家がどのくらいの規模で建てられるか」を決める法規制が必ずあります。
確認を怠ると理想の家が建てられず、住まい計画が大きく狂ってしまうため注意が必要です。
本セクションでは、下記の順番に解説します。
- どんな法規制がある?
- その他のよくある規制
- 住宅地でよくある用途地域
- 購入前に必ず確認しよう
以下、それぞれ解説します。
どんな法規制がある?
土地を購入する前は、まず用途地域・建ぺい率・容積率の3つを確認しましょう。
土地に対して建てられる建物の種類や大きさを決めるルールであり、知らずに買うと希望の家が建たない可能性があるためです。
100坪の土地で考えると、建ぺい率60%・容積率200%で下記の範囲の家を建てられます。
- 1階部分は60坪まで
- 延べ床面積は200坪まで



延べ床面積とは、建物のすべての階の床面積を合計したものを指します。
理想の間取りを実現するためにも、建ぺい率・容積率などの法規制を購入前に必ず確認しましょう。
その他のよくある規制
主要な3つ以外にも、土地には下記のような規制があります。
- 前面道路が狭いと容積率が制限される
- 防火地域・準防火地域は防火仕様が必須で追加費用が発生
- 地区計画や建築協定で屋根形状や外壁色などが制限される
- 道路や隣地の採光を守るための斜線制限で家の高さや形が制限される場合がある
上記の規制も含めて総合的に確認することで、後悔のない土地選びができます。
住宅地でよくある用途地域
各土地に指定された用途地域の特徴を理解して選ぶことが大切です。
どの用途地域かで、静かな住宅街か、商業施設が周囲に建つ環境かが分かります。
住宅地でよくある用途地域は次のとおり。
| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 30~60% | 50~200% | 1〜3階までの低層住宅が中心。小規模な店舗や小中学校はOK。 |
| 第2種低層住居専用地域 | 30~60% | 50~200% | 2階建て以下で150㎡以下の店舗は可。 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 30~60% | 100~500% | 4階建以上のマンションも可能。戸建ても多い。 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 30~60% | 100~500% | 2階建て以下で1,500㎡までの店や事務所も可能。 |
| 第1種住居地域 | 50~80% | 100~500% | 3,000㎡以下の商業施設と共存。住環境を守る地域。 |
| 第2種住居地域 | 50~80% | 100~500% | パチンコ店やカラオケボックスも可。 |
| 準住居地域 | 50~80% | 100~500% | 幹線道路沿い。小規模な劇場や修理工場も可能。 |
建ぺい率や容積率の具体的な数値は、市区町村や地域によって細かく異なるため、購入を検討している土地がある場合は、自治体のホームページなどで詳細を確認しておきましょう。
どんな街並みになる地域か把握し、ライフスタイルに合う土地を選びましょう。
購入前に必ず確認しよう
気になる土地が見つかったら、必ず下記を確認してください。
- 不動産広告の注意書き
- 市役所の都市計画マップ
- 不動産会社やハウスメーカーへの詳細確認
プロにも相談し、購入後に「こんなはずじゃなかった」とならないようにしましょう。
4_地盤調査と追加工事のリスク確認
土地を購入する前は、地盤の状況を確認しましょう。
地盤が弱い土地では、改良工事や擁壁・盛土などが必要になり、想定外の出費につながるためです。
地盤改良では、30坪の住宅であれば20〜30本程度の杭を打つケースが多いですが、軟弱地盤の場合は40本以上になることもあります。
工法や地盤の状況によって費用は80万〜180万円と高額になるため、事前の情報収集が欠かせません。
さらに水はけの悪い土地では床下湿度が80%以上になり、木材が腐食したりシロアリ被害が発生するリスクもあります。
地盤リスクを簡単に調べたい場合は、地盤サポートマップや自治体のハザードマップの活用がおすすめです。



気になる土地が見つかったら、住宅会社に近隣の地盤データを確認してもらいましょう。
売主の許可を得られれば、契約前に地盤調査を実施できる場合もあります。
購入後に後悔しないためにも、早い段階から地盤リスクを確認しておくことが大切です。


5_道路・インフラの状況を確認
土地購入前は、前面道路の幅や上下水道などのインフラ状況を確認しましょう。
インフラ状況の確認を怠ると、思わぬ追加費用や建築制限が発生します。
以下の注意点を押さえておくと安心です。
- 幅員4m未満の道路は「セットバック」が必要
容積率も道路幅に応じて制限される - ブロック塀の撤去費用が約10万~50万円発生することも
- 位置指定道路は将来の補修費用を住民が負担
セットバックとは、道路中心から2m後退して家を建てることで、建築可能な面積が狭くなります。
- 本管が前面道路まで来ている場合:引き込み費用は約50万円
- 本管が遠い場合:延長工事で約100万~300万円かかることも
- 排水勾配が取れない土地:
・かさ上げ工事…約80万~120万円
・排水ポンプの設置…約30万~50万円
調査方法は下記のとおりです。
- 市役所の上下水道台帳や道路台帳の確認
- 建築会社や不動産会社による現地調査
前面道路や上下水道などのインフラ状況を事前にしっかり調べることで、想定外の出費やトラブルを避けられます。
6_ハザードマップで災害リスクを把握
土地の購入前には、必ずハザードマップを使って災害リスクを確認しましょう。
安い土地ほど、実は災害リスクが隠れていることが多く、購入後に大きな費用負担や被害を受ける可能性があります。
特に注意すべき災害リスクは下記の3つです。
- ハザードマップで警戒区域に指定されている土地
- 液状化の危険性が高い土地
- 浸水想定区域ギリギリの土地
以下、それぞれについて簡潔に解説します。
警戒区域指定の土地
ハザードマップで警戒区域とされた土地は、土砂災害や浸水のリスクが高く、実際に大きな被害が発生する可能性があります。
液状化の危険性が高い土地
液状化の危険性が高い土地は、埋立地だけでなく、昔の川跡や地下水位が高い地域でも発生します。
対策工事は30坪で300万円程度、条件次第では1,000万円を超えることもあります。
浸水想定区域ギリギリの土地
浸水想定区域ギリギリの土地は、近年の災害規模拡大により想定外の浸水被害が起こる可能性があります。
床上浸水になると建物の構造自体がダメージを受け、最悪の場合は建て替えが必要になることも。
上記のようなリスクを見落とさないためにも、災害リスクの有無を事前に確認しましょう。
確認には以下の2つの方法があります。
- 重ねるハザードマップ(国土交通省)
- 各自治体の土砂災害警戒区域マップ
重ねるハザードマップはスマホから簡単に確認でき、洪水・土砂災害・津波など複数のリスクを重ねて確認できます。各自治体のマップでは、より詳細なハザード情報を確認可能です。
仮に警戒区域に指定されていても、擁壁を設置したり地盤改良をすることで対策可能なケースもあります。



自然災害のリスクは年々高まっています。
ハザードマップを活用し、安全に暮らせる土地かどうかをしっかり確認しましょう。
7_様々な条件での現地確認とリサーチ
土地を購入する前は、時間帯や天気を変えて何度も現地を確認することが大切です。
1回の見学だけでは気づけないポイントが多く、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔する原因になります。
以下を目安にチェックしてみましょう。
- 騒音:早朝や夜間の車や店舗の音
- 街灯の明るさ:夜の道の暗さ・安全性
- 水はけ:雨の翌日に側溝や庭を確認
- 日当たり:真西からの強い日差しや周囲の建物の影
- 近所の雰囲気・治安:ゴミ捨て場の様子や空き家の多さ
- 地域ルールや負担:自治会費、祭りや行事の有無
さらに近所の住民に話を聞いてみると、その土地でのリアルな暮らしが見えてきます。
8_境界杭・測量状況の確認
土地購入前は、必ず境界が確定しているかを確認しましょう。
境界が曖昧なまま契約すると、後から深刻なトラブルに発展するリスクがあります。



実際、不動産売買で最も多いトラブルが「境界問題」です。
ブロック塀やフェンスを境界線だと思い込んで建築を進めた結果、隣地への越境が発覚し、訴訟や再施工が必要になるケースもあります。
購入前に確認しておきたい主なポイントは下記のとおりです。
- 不動産資料に「確定測量図」や「筆界確認書」があるか
- 境界杭・境界標が全ての角にしっかり設置されているか
境界杭がない場合は、契約前に売主負担で確定測量を行うよう交渉しましょう。
もし買主が確定測量を依頼する場合、下記のような費用と期間がかかります。
- 隣地所有者との確認:約40~50万円
- 道路や公有地との確認:約60~80万円
- 調査・立ち会い・書類作成:約2〜4ヶ月
安心して家を建てるためにも、契約前に境界をしっかり確認し、曖昧なまま決断しないようにしましょう。
9_安い土地の隠れたコストを確認
安い土地には隠れたコストがあるため、購入前に追加費用を必ず確認しましょう。
相場より安い土地は、造成費や工事費、建築制限などの問題を抱えているケースが多く、暮らしやすさや総額に影響を与えるためです。
特に注意すべき安い土地のリスクは以下の4つです。
- 旗竿地
- 高低差や擁壁がある土地
- 変形地
- 建築条件付き土地
以下、各土地の特徴とリスクを簡潔に紹介します。
旗竿地
旗竿地は道路から細い通路を通って奥に家を建てる形状で、駐車が不便になりがちです。
電柱から電気を引くために約20万円以上の中継ポールが必要になることや、排水の勾配を確保するために盛土・給排水延長工事で数十万円以上かかる場合もあります。


高低差や擁壁がある土地
高低差がある土地では、擁壁の有無や状態を確認することが非常に重要です。
新たに擁壁工事が必要な場合、高さ1mで約30万~50万円、2m以上になると法律上「崖」とみなされ構造計算が必要でさらに高額になります。
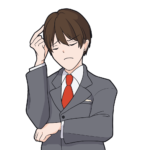
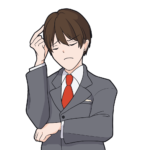
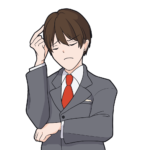
古い擁壁がすでに設置されている場合も注意が必要です。
法令上の認可を得ていない擁壁があると、崩れた際に全額自己負担で再構築が必要になる可能性があり、数百万円規模の工事費が発生することもあります。


変形地
変形地は三角形や台形の土地で相場より15〜20%安いこともありますが、設計が難しく施工費や設計料が高くなりやすいです。
デッドスペースが増え、暮らしにくい間取りになるケースも少なくありません。


建築条件付き土地
建築条件付き土地は土地を買うと同時に家を建てる会社が決まっている仕組みで、土地は安く見えても建物でしっかり利益を取るビジネスモデルです。
土地は安く見えても、建てる住宅の価格が割高になるケースが珍しくありません。


見た目の価格に惑わされず、トータルコストで本当にお得かどうかを確認しましょう。
10_条件7〜8割での早期決断
これまでの9つのチェックポイントをクリアした後は、希望条件の7〜8割を満たす土地であれば、早めに決断することが大切です。
100%理想の土地に出会えることは非常にまれで、条件の良い土地ほど競争率が高く、迷っている間に売れてしまうことも多いためです。
その場で決断できるように、以下のような準備を整えておきましょう。
- 家族全員で現地を確認し、その場で結論を出せる体制を整える
- 工務店や住宅会社を決めておき、建物プランや総予算を共有しておく
- 希望条件は少し幅を持たせ、選択肢を狭めすぎない
- 住宅ローンの事前審査を終え、資金計画に不安がない状態にする
- 担当者には「良い土地があれば即決する意思がある」ことをしっかり伝える
完璧を求めてチャンスを逃すよりも、納得できる7~8割の条件が揃っていれば、迷わず決断する勇気が、土地探しを成功に導くポイントです。
\ 無料・たった1分・建築士が監修 /
土地探しがうまくいかないときの3つの対処法
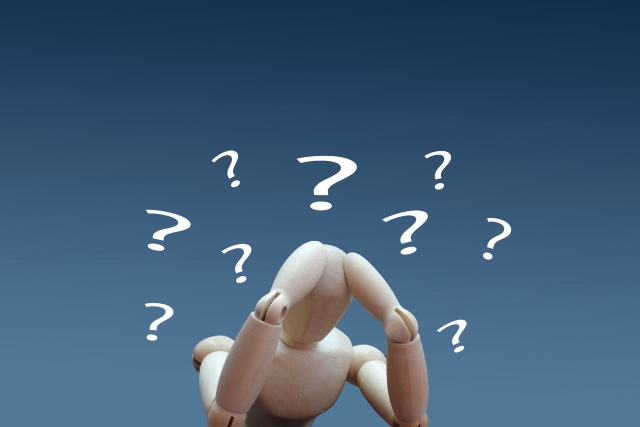
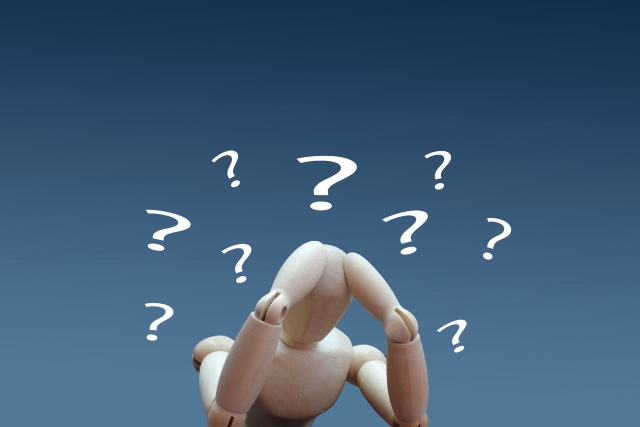
思うように土地が見つからないときは、条件や考え方を見直すことが解決の近道です。
希望を整理し、柔軟に発想を変えるだけで、理想の家づくりが現実に近づくことはよくあります。
以下の3つの方法を試してみましょう。
- 希望条件を見直して柔軟に考える
- 他の方法で希望条件をカバー
- 古家付き土地の検討
それぞれ解説します。
1_希望条件を見直して柔軟に考える
土地探しが進まないときは、条件を見直して優先順位をつけることが大切です。



希望を詰め込みすぎると合う土地はなかなか見つかりません。
例えば「整形地・南向き・広さ・駅近・価格」と全て求めれば物件はほぼゼロです。
最優先の条件だけを残し、他は思い切って緩めることで選択肢が一気に広がります。
具体的な方法は、こちらの記事も参考にしてください。
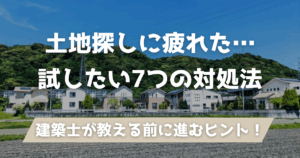
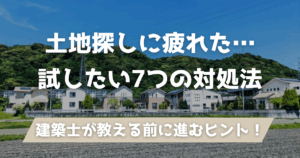
完璧を目指すより、妥協点を整理して現実的に考える方が理想の家に近づけます。
2_他の方法で希望条件をカバー
土地のデメリットは家づくりで補える場合があります。
条件に満たない土地でも、設計の工夫で快適に暮らせるからです。
例えば、下記のような工夫ができます。
- 狭い土地の場合:間取りの工夫や吹き抜けを取り入れて、圧迫感のない空間に
- 日当たりが悪い場合:2階リビングや天窓を活用して、採光をしっかり確保
土地+建物の総合プランで考えれば、選べる土地はもっと増えます。
\ 無料・たった1分・建築士が監修 /
3_古家付き土地の検討
更地にこだわらず古家付きも視野に入れるとチャンスが広がります。
古家付き土地は見た目が悪く敬遠されがちで、ライバルが少なく価格交渉もしやすいからです。
交渉次第で「解体更地渡し」にしてもらえることも多く、ネットでは中古戸建として掲載されている場合もあります。
更地だけでなく古家付きまで探すことで、理想の家を建てられる可能性はぐっと高まります。
まとめ|10のコツを押さえて理想の土地を見つけよう


今回は、土地探しで失敗を防ぐ具体的な方法についてお話ししました。
希望に合う土地を探し出すには、1つの方法に頼らず、複数のルートを同時に活用することが効果的です。
- 自分でネットや資料請求で情報収集
- ハウスメーカー・住宅会社への相談
- 地元の不動産屋巡り
特に、不動産屋に直接訪問して顔を覚えてもらったり、住宅会社を決めて土地が見つかった際に迅速な対応を依頼したりすることが大切です。
土地探しの失敗には、予算配分の間違いや法規制の見落とし、災害リスクの軽視といった知識不足などが背景にあるため、下記の10の方法を押さえましょう。
- 総額予算の決定と適切な配分
- 住宅会社選定と土地探しの連携
- 用途地域・建ぺい率など法規制の確認
- 地盤調査と追加工事のリスク確認
- 道路・インフラの状況を確認
- ハザードマップで災害リスクを把握
- 様々な条件での現地確認とリサーチ
- 境界杭・測量状況の確認
- 安い土地の隠れたコストを確認
- 条件7〜8割での早期決断
知らないと、追加でコストがかかるリスクがたくさんありますので、事前に勉強しておきましょう。
ちなみに本記事では、補足として土地探しがうまくいかないときの3つの対処法をお伝えしました。
- 希望条件を見直して柔軟な考え方
- 他の方法で希望条件をカバー
- 古家付き土地の検討
以上の内容を知っておけば、あなたの土地探しで後悔する可能性を減らすことが出来ます。
ここまで読んでくださった方は、そろそろ動き出すタイミングかもしれません。



後悔しない土地探しのために、まずは資料請求してみてはいかがでしょうか?
家づくりは下調べをせずに進めると完成後に「え?もっと良い会社あったじゃん!調べておけばよかった〜!」と後悔する人が続出します。
そのため、まずやるべきは
とはいえ、一つずつ調べていくのも大変なので、最近は、一度にカタログが取り寄せできる「一括資料請求サイト」が人気です。
しかし、一括資料請求サイトということもあり、サイト選びを間違えると、カタログが届かなかったり、強引な営業を受けることにもなります。
良質な資料請求サイトを利用して、まずは興味がある会社をピックアップしましょう。
この3つは、大手企業が運営しており、登録されている住宅会社は厳しい審査をクリアしている会社のみです。
そのため、カタログを取り寄せたからといって強引な営業をしてこないため、まずはカタログを集めて情報収集する家づくり初心者さんには大変メリットの大きいサービスです。
\ 間取り・見積書まで欲しいなら/
\ 営業電話はNG!慎重派のあなたへ/
\ とりあえず安い会社を知りたいなら/
ぜひ、信頼できる一括資料請求サイトを利用し、効率よく家づくりを進めてください。